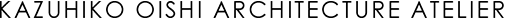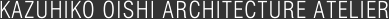2023.10.17
ホークス残念!
昨夜のホークス対ロッテのCS最終戦はとても引き締まった試合で久しぶりに
最後までテレビ観戦しましたが、最後はこれまでの2年間(昨年の最終戦V逸、今期最終戦の3位 確定)を象徴するような負け方で終わってしまいました。
10回表の攻撃はこれまでの藤本監督らしくないぐらい選手交代がはまりやっと3点を先制。
通常延長戦表に3点も取られれば裏の攻撃で取り返すのは難しくほぼ勝利は確実な筈ですが
10回裏のピッチャーを津森と藤本氏が告げた時点でボクはえッ!!こんな大事な場面で津森?
どういうつもり?と思いました。
津森は球種が少なく直球中心にしか組み立てが出来ないタイプで
大事な場面での信頼性は低いにも関わらず、何故か藤本氏がよく使う理由が理解できません。
以前の試合において先発キャッチャーが珍しく嶺井で途中継投で津森に変わり何球か
投げた時点でキャッチャーを甲斐へ替えたことがありました。結果的に甲斐に替えても
津森は打たれてしまいましたが敗戦後の監督のコメントが津森と嶺井の組み合わせが
シーズンにおいてほとんどない為変えたということに対し、ネット裏のファンからはだったら
甲斐ばかり使わずどうしてもっと嶺井を使っておかないんだという声が上がりました。
昨日の試合で甲斐の代わりに新人の生海を代打に出した為、(生海は2軍戦では当たっていましたが過去1軍の試合では代打で結果を残せておらずこんな大事な場面で使うルーキーではないと思うのですが—-)キャッチャーが嶺井に変わりましたがその嶺井に対し津森を使ったのは前回の理由に対し整合性がなくおかしいという多数の意見があります。
今年のホークスのピッチャー陣は先発が総崩れで確定できないというボロボロの状態になった原因は今年からピッチングコーチになった斉藤和巳に責任があると思っています。
(モイネロの離脱という理由があるものの昨年は藤本体制でもこんなに状況は悪くなかった)
また、打撃陣ではキャプテンだった柳田、チャンスに全く打てずバットをただ振り舞わすだけでノーアウト3塁でもワンアウト1,3塁でも3球3振というケースが多々ありました。
もっと1球1球大事にして欲しいし、試合中負けているにも関わらずへらへらしており
髪型も変でキャプテンとしての自覚が全く欠けていたと思います。
もうこれから柳田を特別扱いせず、場合によってはトレードに出してチームを一新する
覚悟も必要かと思います。
数多くのファンのフラストレーションが爆発するのを知ってか敗戦後1時間20分して
球団より藤本監督の退任と小久保氏の1軍監督就任がまるで準備していたかのように
早々に発表されました。
小久保氏もこれまで全日本の監督などで評価が低く、ホークスの2軍監督で研鑽を積まれていましたが選手をまとめ引っ張っていく情熱は誰よりもあると思っています。
柳田を含め弛んでしまったホークスの選手たちの気持ちを緊張感を持って
引き締めて欲しいと思っています。
(個人的な意見としてプレイ中にチューインガムをかむのはアメリカ人ではないので是非止めて欲しい)
2023.09.30
ホームページについて
先日、ホームページのマイナーチェンジのお知らせをこのブログでご案内いたしましたが
その後、パソコンでのデータが重いことやギャラリーでの物件が以前に比べ
減っていること等があり再度調整を行っています。
大変申し訳ありませんが、パソコンの方はF5ボタンを押されると最新のに
切り替わりますのでよろしくお願いいたします。
2023.09.26
スキッピケーション
先日、情報番組で小学校が取り組むラーケーションというシステムの紹介があっていました。
愛知県が初めてらしく(学ぶ)learningと(休暇)vacationを組み合わせた造語です。
仕事上日曜日に休めない保護者にとって1年間に3日まで、平日に子供を休ませても欠席
扱いにならず休日をいろんな学びとして過ごせるシステムだそうです。
お父さんやお母さんたちが日曜日に仕事で家族で一緒に中々過ごせないご家族や
皆勤賞を狙っているまじめなお子さんにとっては今のところ わずか3日ですが
有難いシステムだろうと思います。
そんな色々な事情があるご家庭にとって不謹慎かもしれませんが
ボクは学校に毎日行くことに価値を見出しておらず、
小学生時代は何かにつけて休んでいました。
あーきょうは何となく行きたくないなあと思うと母にお腹が痛いと言ってズル休み。
熱があるみたいなので休ませて欲しいと言って熱を測ると残念!6度9分で結局行くことに。
色々理由をつけて休んでも母からは怒られませんでした。
放送では3日間休むことに勉強がわからなくなると心配されているお母さんもいましたが
ボクからすれば3日ぐらいなんか何も問題ないし1ヶ月3日でも良いぐらいだと思います。
ちなみにズル休みは英語でskipと言うそうです。
であればボクのはスキッピケーションになるかも
2023.09.24
これからの公共建築の在り方

日曜日は通常家でだらだらと1日を過ごしていまいがちですが
今日は心機一転、心を入れ替え、JIAからの情報で知った佐賀県鹿島市に出来た
古谷氏のNASCA設計による鹿島市民文化ホールの見学会に行って来ました。
2年前に完成した当アトリエ設計のTHE Lがある武雄からは近く、
福岡からは高速を使って1時間半ぐらいの場所です。
構成はきわめてシンプルで楕円状の外郭内にフライタワーと観客席を伴った直方体の
コアを配置し外周部を回る白いリング状の壁はコアである直方体から持ち出されています。
さらにその外周部に避難経路を含めたスロープ状のペデストリアンデッキが巡らされています。

エントランスから入って飛び込んでくるのが客席とクローズされていないこの写真の手前の
スペースでここは可動間仕切り(ホール正面のたてリブが入った打ち放し壁の裏側に収納されています)によって客席があるホールと切り離すこともできる展示スペースだそうで
限られた面積的制約の中で多目的な使用方法に対応できるシームレスな
構成になっています。
したがってホールでありながら自然光が入る気持ち良いスペースになっています。
(上部開口部には電動の遮光スクリーンが入っています)

舞台と袖の多目的スペースが繋がった不思議な空間

客席は2階も含め750席ありここにも一般的なホールでは見かけない自然光が入るトップライトが取られています。上部8角形のトップライトを中心にフライタワーの上部造形は渦巻き状に
8分割されコンクリート打ち放し仕上げでズレながら組み合わされています。

劇場といえば天井部のデザインにこだわりがちですがこのように構造を露出させても
自然光が入るのであればもっと自由な使い方が可能になると思います。


鹿島市は嬉野市の隣にある有明海に面した人口3万人の小都市で今回の市民文化ホールは
これまでの箱物建築とは違い、身の丈に合わせた多目的性を追求した建物で
非常に好感の持てる建築だと思いました。
2023.09.19
定期演奏会

妻が所属する大学OBオーケストラ(橘フィル)の年1回の定期演奏会にスペースキューブの
梅崎ご夫妻をお誘いし聴きに行って来ました。
今年の曲目は シベリウス;交響詩「フィランディア」 (10分)
ドリーブ ;バレエ音楽「シルヴィア」組曲 (20分)
ベートーヴェン;交響曲第7番ィ長調 (40分)
みなさん知り合いがいると思い気軽な気持ちで来て頂き、アマチュアながらも演奏は
本格的であることもあり、いつもびっくりされています。
また、毎年入場時に渡されるパンフレットでの軽妙洒脱な曲目説明により
長い時間にも関わらず飽きずに楽しく聴くことができます。
それにしてもベートーヴェンの第7は非常にスピード感があり当時であれば
現代のロックに近いと思いました。